最近、専属AIの設計について説明する際に
「小説一冊分の物語をインストールしている」
という表現を使うようになりました。
この表現を聞いて、
「なぜ小説一冊分なの?」
「どうやってその分量を決めたの?」
と疑問に思われた方もいるでしょう。
今回は、この「小説一冊分」という分量設定の裏側と、そこに込めた設計思想について詳しくお話しします。
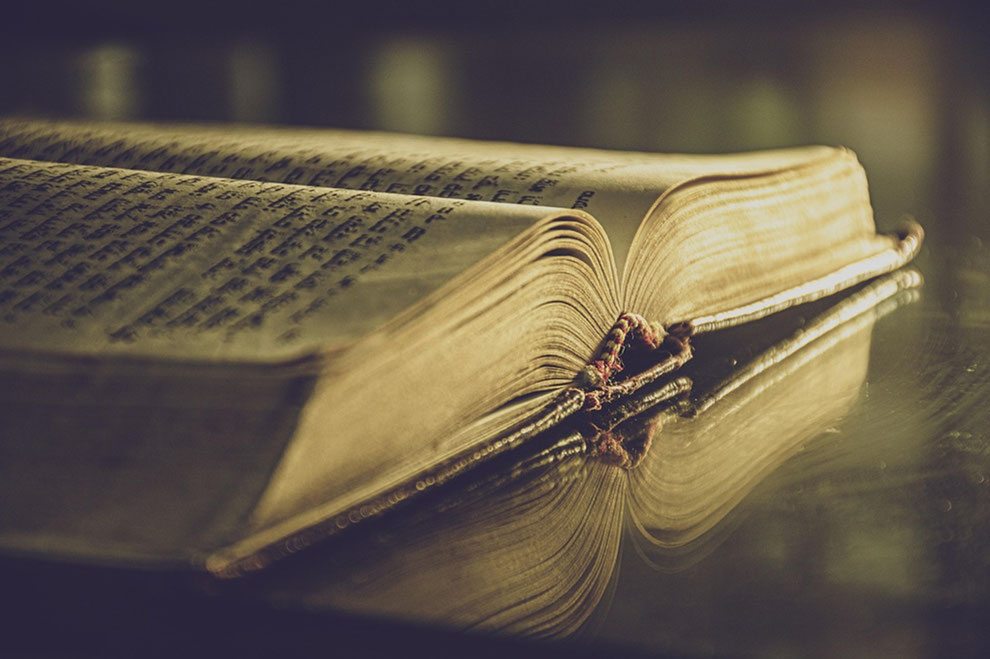
「分量ありき」ではなかった初期の試行錯誤
最初から「小説一冊分」を目指していたわけではありません。
専属AIの設計を始めた頃は、クライアントから聞き取った情報を、思いついた順にAIに学習させていました。
いわゆる「行き当たりばったり」です。
でも、これでは明らかに不十分でした。
クライアントとの対話を重ねるうちに
「あ、これも伝えておくべきだった」
「この背景情報が抜けてた」
という「情報の穴」が次々と見つかるのです。
そこで試したのが「情報量を2倍、3倍に増やす」というアプローチ。
でも、ただ量を増やしただけでは「物置部屋」のようなAIになってしまいました。
情報は多いのに、的確な応答ができない。
関連性のない情報が混在して、かえって混乱を招くのです。
「MECE」という武器との出会い
転機になったのは、コンサルティング時代に叩き込まれた「MECE(モレなく、ダブりなく)」の考え方を思い出したことでした。
専属AIの知識も、企業の戦略資料と同じように構造化すべきだと気づいたのです。
- モレなく:クライアントの価値観、事業背景、顧客像、サービス詳細、言葉遣いの癖まで、必要な情報を漏らさず整理する
- ダブりなく:同じような情報を複数の視点で重複して記載せず、一つ一つの情報に明確な役割を持たせる
この「MECE化」を徹底して行うと、不思議なことに情報量が一定のボリュームに収束していくのです。
なぜ「小説一冊分」という表現なのか
ある日、完成した専属AIの知識ファイルを眺めていて、ふと思いました。
「これ、文庫本くらいの分量だな」
実際に文字数を数えてみると、だいたい8万~12万字。
これは確かに小説一冊分でした。
でも、なぜこの分量なのでしょうか?
これは心理学的な現象ではないかと考えています。
人間が一人の人物を「深く理解している」と感じるために必要な情報量は、その人の「人生の物語」を一冊の本として読み切れる程度なのではないか、と。
友人や家族のことを考えてみてください。
その人のことを「よく知っている」と感じるのは、その人の価値観、過去の経験、口癖、考え方の癖、好き嫌いなどを、まるで一冊の小説を読んだかのように理解しているからではないでしょうか。
「物語」という構造の重要性
ここで重要なのは、単に「小説一冊分の分量」ではなく、「小説のような物語構造」で情報を整理していることです。
主人公(クライアント)の設定
- 何を大切にしているか(価値観)
- どんな経験をしてきたか(原体験)
- 今、何に悩み、何を目指しているか(現在の立ち位置)
舞台設定(ビジネス環境)
- どんな業界で活動しているか
- 顧客は誰で、どんな課題を抱えているか
- 競合他社や市場環境はどうなっているか
プロット(事業の展開)
- これまでどんな挑戦をしてきたか
- 成功と失敗の経験から何を学んだか
- 今後どこに向かおうとしているか
文体(言葉遣いと思考パターン)
- どんな言葉を好んで使うか
- どんな論理展開をする癖があるか
- 相手によってどう話し方を変えるか
この「物語構造」で整理することで、AIは単なるデータベースではなく、クライアントという「一人の人物」を理解した相談相手になれる。
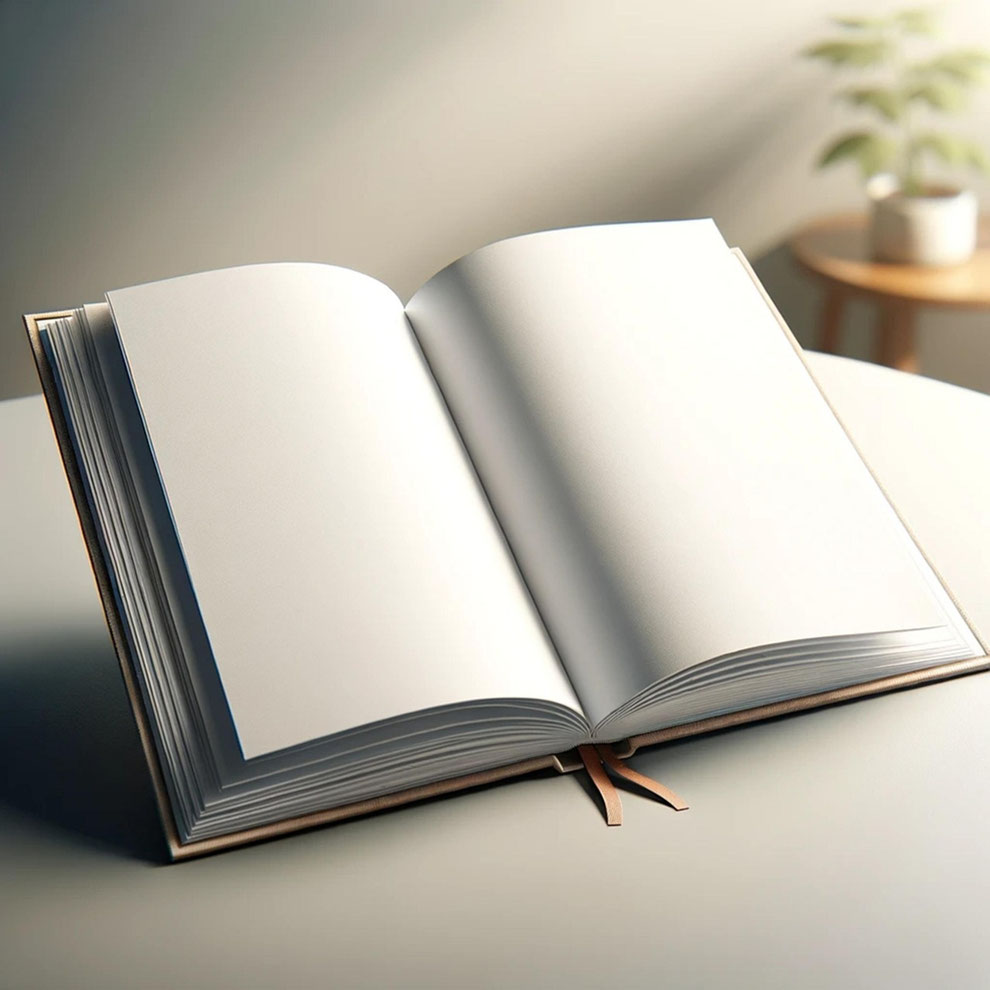
「これ以上増やしても改善しない」境界線
興味深いのは、小説一冊分を超えて情報を増やしても、専属AIの理解度がそれほど向上しないということです。
現在のAI技術の限界でもありますが、同時に人間の認知特性にも関係していると考えています。
人間も、あまりに多すぎる情報を一度に処理しようとすると、かえって本質を見失います。
小説一冊分というのは、人間が「一人の人物」を深く理解するのに適した情報量なのかもしれません。
## 従来の対話型AIの限界を乗り越える設計思想
一般的なChatGPTやClaudeなどの対話型AIとの決定的な違いは、この「事前に構造化された小説一冊分の物語」があることです。
通常の対話型AIでは、会話の中で断片的に情報を教えても、それらがAI内で体系化されることはありません。
まるで、小説をバラバラにちぎって、ランダムな順序で読んでいるようなものです。
一方、専属AIでは最初から「完全な物語」が刻み込まれています。
だからこそ、どんな相談をされても、その背景にある「あなたの物語」を踏まえた応答ができるのです。
「小説一冊分」に込めた想い
この表現には、もう一つの想いが込められています。
それは「あなたのビジネスは、一冊の小説になるほど価値のある物語だ」というメッセージです。
多くのスモールビジネスオーナーは、自分の事業を「大したことない」と謙遜します。
でも、その事業に込められた想い、乗り越えてきた困難、お客様との出会い、そして未来への希望は、優に「一冊の小説」に値する物語なのです。
専属AIを作ることは、その物語を大切に整理し、AIという形で永続化する作業でもあります。
次の進化への布石
現在、AIコンサル工房では「小説一冊分」を一つの基準としていますが、AI技術の進歩とともに、この基準も進化していくでしょう。
でも、「人を深く理解するためには物語が必要」という本質は変わらないと思います。
技術が進歩しても、人間の心を動かすのは、結局のところ「物語の力」です。
「なぜ小説一冊分なのか?」
それは、あなたという人を、AIが本当に理解するために必要な、最小にして最適な物語の分量だからです。
そして何より、あなたの事業が、確実に一冊の小説に値する価値ある物語だからです。
